医学教育・国際化推進センター(CMEI)
京都大学医学教育・国際化推進センター(CMEI)は、入学時から卒業時までを一貫してサポートする教育セクションであり、本事業の教育面での中核を担うとともに、事業全体をマネジメントする役割を果たします。本学では、学部生に対して世界に羽ばたくPhysician Scientistの育成を目指して特徴的なカリキュラムを構築しています。研究者育成については、MD研究者育成プログラムという選択カリキュラムを提供しています。これは、基礎医学研究に興味を持つ学生が入学直後から研究に親しみ、従事することで我が国を牽引する研究者を養成することを目的としているものです。1年次には40名を超える学生がプログラムに参加し、最先端の研究に触れ、スキルを身に着けています。4年次のマイコースプログラムではカリキュラム内での短期留学も可能な研究期間を設けています。附属病院の初期研修プログラムには基礎研究医プログラムを運用し、研修医の期間も研究マインドを保持して大学院でさらに研究に専念できる連携システムをとっています。
臨床教育は1年次の早期体験実習に始まり、多職種連携教育も組み込み、基本臨床実習では学内のみならず地域の医療機関で幅広い経験を積み、さらに6年次にはイレクティブ実習として海外でのクリニカルクラークシップ参加も含めた多彩な実習の機会が得られます。
Kyoto-NEXT事業では、このような枠組みを背景に、研究者育成プログラムのさらなる発展と臨床教育の飛躍的な充実を実現し、今後臨床研究を目指す学部生・大学院生の支援をさらに充実化し、臨床と基礎分野の連携を担う人材の育成を目指します。
互いを尊重し、教えあう文化の醸成と発信
現代の医療教育において、医療者同士が互いを尊重し、教えあう文化の重要性はますます高まっています。臨床現場での経験や知識は、個々の医療者が身につけるだけでなく、チーム全体で共有され、相互に補完されることで、より良い医療を提供することが可能になります。
「屋根瓦式教育」は、近い世代の先輩が後輩を指導し、互いに学び合う仕組みです。この伝統的な教育手法は、単なる知識の伝達に留まらず、相互に教え合う文化を通じて、医療現場で求められる人間性やチームワークを育むものです。私たちは、この屋根瓦式教育を基盤に、「臨床も、研究も、教育もチームで行う」というスローガンのもと、次世代の医療人材の育成を推進していきます。本事業では、研究面では従来のMD研究者育成プログラムにおいて、臨床面では臨床実習において屋根瓦式教育を推進し、「Teaching is Learning twice」を実践することで、持続可能な指導サイクルを回していくことが可能です。
具体的には、以下の取り組みを通じて、教育体制を強化していきます。
① チームベースの学習と教育環境の整備
大学や附属病院における様々な場で、それぞれの知識やスキルを共有し、互いに教え合う機会を提供します。このプロセスを通じて、学習者は自らが学んだことを他者に教えることで、より深い理解と実践力を身につけます。
② 尊重と信頼に基づくコミュニケーションの推進
学習者一人ひとりの意見や経験を尊重し、対話を通じて学び合う文化を醸成します。相手を尊重し合うことで、安心して質問や提案ができる環境を作り出します。そのために、「どのように教えるか」という教育、いわゆるFD(Faculty Development)を重視し、安心して建設的なコミュニケーションができるよう支援します。
③ 指導と学びのサイクルの強化
教える側も常に学び続ける姿勢を持ち、学習者との対話を通じて自己研鑽を積むことを促進します。これにより、指導者も学習者も共に成長するサイクルが生まれます。
屋根瓦式教育は、単なる教育法ではなく、医療における人材育成の柱です。この手法を通じて、私たちは臨床、研究、教育の全てをチームで行う文化を醸成し、次世代の医療現場で活躍する医療者を育ててまいります。
今後とも、皆様のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
医学教育・国際化推進センター
医学教育学 教授
K-NEXT 臨床教育体制強化責任者
片岡仁美

メンバー紹介

准教授
三好 智子 ミヨシ トモコ (Tomoko Miyoshi)
高知医科大学卒業後、岡山大学病院にて内分泌内科専門医として臨床・研究・教育に従事。医学教育専門家、医療者教育学修士。研究テーマは、医学生のプロフェショナルアイデンティティの形成過程と影響因子の解明。Kyoto NEXTでは臨床実習支援、進捗管理、教育評価・研究を担当し、主な取り組みとしては若手教育者へのオンラインFDコースである「教育をもっと魅力的に! Kyoto NEXT Educators’ Lab」のマネジメントを行っている。
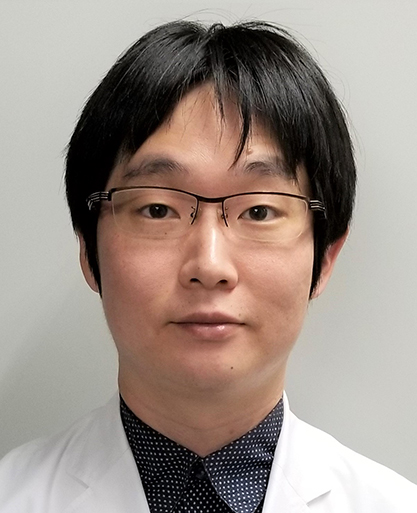
講師
生野 真嗣 イクノ マサシ(Masashi Ikuno)
京都大学卒業後、洛和会音羽病院にて初期研修・後期研修を行い、京都大学脳神経内科教室に入局。パーキンソン病に関する病態研究に従事していたが、2023年8月より医学教育部門に参画。Kyoto NEXTでは事務局代表として事業全体の総合事務・予算管理・ペースメイクを担当。

助教
時信 亜希子 トキノブ アキコ(Akiko Tokinobu)
医学教育・国際化推進センターにて医療職支援のための「KUSNoKIプロジェクト」に従事。医学生・医師の共感性(empathy)に関する研究にも取り組んでいる。Kyoto NEXTではKUSNoKIプロジェクトとの連携の他、医学教育学部教育部門、IR(Institutional Research)を担当している。